
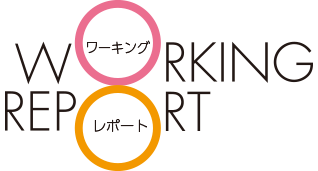
固い岩盤を慎重に掘り進み
徐々に姿を現しつつある
小樽の新幹線
北海道新幹線建設局 小樽鉄道建設所
北海道の産業と近代化を支えた小樽。その小罇市の郊外で、北海道新幹線の建設工事が進行中だ。
山間の狭い土地を活用し、周辺環境への影響を最小限に抑えながら着々と進むトンネル工事現場の現在を報告する。
文:栗原 景(フォトライター) 写真:丸山達也
鉄道・運輸機構だより2021秋季号
※文はリモート取材により作成し、撮影は函館市在住のカメラマンが担当致しました。
固い岩盤を慎重に掘り進み徐々に姿を現しつつある小樽の新幹線
北海道の産業と近代化を支えた小樽。その小罇市の郊外で、北海道新幹線の建設工事が進行中だ。山間の狭い土地を活用し、周辺環境への影響を最小限に抑えながら着々と進むトンネル工事現場の現在を報告する。
文:栗原 景(フォトライター) 写真:丸山達也
鉄道・運輸機構だより2021秋季号
※文はリモート取材により作成し、撮影は函館市在住のカメラマンが担当致しました。
北海道の開拓を支えた港町・小樽
「ぜひ、ここから小樽市街を見ていただきたいと思ったんです」
標高532mの天狗山山頂で、小樽鉄道建設所の羽生田康雄所長が言った。目の前に、小樽市街と日本海が広がっている。
「小樽は、明治以来北海道開拓の重要な港湾で、交通と物流の要衝でした。北海道最初の鉄道は手宮・札幌間を結び、ここからもその線路跡が見えています」
少し歩いて、東側の第三展望台に移動すると、眼下の谷にオレンジのネットで囲った一角が見えた。
「新小樽(仮称)と呼んでいる新駅の予定地です。まだ工事には着手していませんが、5月に小樽市へ新駅のデザインコンセプト作成を依頼しました。1年をめどに作成していただき、それを元に当機構で複数のデザイン案を作成します」
北海道新幹線新函館北斗・札幌間は、令和12年度末の開業を目指して各地で工事が進められている。平成29年4月に発足した小樽鉄道建設所は、余市町から小樽市を経て札幌との市境付近まで、22.0kmの土木施設建設を担当する建設所だ。現在担当の5工区は全てトンネルである。施工する工事の大部分が、トンネル建設である。この春から所長を務める羽生田所長は埼玉県出身。九州新幹線の工事監理業務をはじめ、リニア中央新幹線の技術検討業務、大阪で準備が進むなにわ筋線など都市鉄道の基礎調査などや、鉄道建設に関わる幅広い業務を手掛けてきた。
小樽鉄道建設所は、後志(しりべし)トンネル(一部)、朝里トンネル、札樽(さっそん)トンネル(一部)の3トンネルを5工区に分けて担当している。現在は4工区でトンネル掘削工事が進行中だ。天狗山から下り、まずは起点方の後志トンネル塩谷工区に向かった。



固く安定した岩盤を発破工法で掘り進む
道道956号の交差点から小樽市道を経て林道に入り、塩谷川に沿って林道を約2km進んだ奥に、後志トンネル塩谷工区の斜坑入口がある。ここから地下に入り、さらに約10%の下り勾配を約2km下ったところが後志トンネルの本坑だ。全長19.99kmのトンネルで、そのうち塩谷工区は4050m。平成30年11月から斜坑の掘削が始まり、令和3年9月現在、本坑の掘削が1156mまで完了している。
「この辺りの地質は、マグマが固まった安山岩を中心とする堅い岩でできています。土被り、つまりトンネル天端から地上までの距離は最大約550mあります。安定した地盤ですので、発破工法による補助ベンチ付き全断面工法で掘削し、発生土の搬出についてはベルトコンベアを使用しています」
羽生田所長が説明する。発破工法とは、火薬を使った掘削方法だ。塩谷工区の地質は、土というよりは岩盤に近い。機械による掘削は難しいため、ドリルジャンボと呼ばれる重機で掘削の最前面である切羽に削孔し、火薬を装填して岩を砕く。発破は振動や音を伴うため、民家近傍では火薬量を最低限に調整して実施される。
また、後志トンネルでは全断面を一度に掘削する全断面工法を採用しており、トンネル断面を上下に分けて、半分ずつ掘削するベンチカット工法に比べ、作業空間が大きく取れ大型機械を効率的に使用できる。地質が極めて良好な場合に用いられる工法で、発破工法と組み合わせて使われることが多い。発破によって生じた発生土は、ベルトコンベアで坑外の仮置き場に搬出される。
トンネル内に立つと、トンネル断面の様子が奥の切羽付近と手前で異なることに気付いた。
「塩谷工区の地盤は現在大変安定していますが、余市町と小樽市の境にあたるこの地点から地質が変わります。今後は地山の圧力が増すことが予想されるため、断面を支える鋼製支保工の建て込みを開始しました」
鋼製支保工はアーチ状のH形鋼で、掘削した壁面に1~1.2m間隔で建て込むことで地山を支保する。次にコンクリートを吹き付け、放射状にロックボルトを打ち込むことで地山の保持力を利用してトンネルを支える。これをNATM工法といい、現代の山岳トンネルでは標準的な工法だ。小樽鉄道建設所が担当するトンネルはすべてNATM工法を採用している。
塩谷工区から林道を引き返す途中、整地された広場のような場所に立ち寄った。
「ここは、トンネルを掘ることで発生する対策土の受入地です」
小樽鉄道建設所が担当するトンネルからは約200万立方メートルの掘削土が発生する見込みだが、北海道の土には、一部にセレン、砒素といった自然由来の重金属等を微量に含むものがある。トンネル発生土および堅硬な岩は環境省が定める土壌汚染対策法の適用対象ではないが、鉄道・運輸機構では周辺環境に影響を与えることがないよう、国土交通省の「建設工事における自然由来重金属含有岩石・土壌への対応マニュアル」に基づき、対応策を第三者委員会での審議・検討を踏まえ決定しているのだ。ここは小樽市が用意した土地で、今後9万立方メートルの対策土を受け入れる予定だ。


地質の状況に合わせて最適な施工方法を選択する
続いて同じく後志トンネルの天神工区へ。先ほどまで山深い林道にいたが、車で10分も走ると住宅街に出た。天神工区は後志トンネルの一番終点の方の工区で、延長は4475m。土被りは最大約540mで、9月1日現在終点方坑口から393mの地点まで掘り進んでいる。
「このトンネルを抜けると、新小樽駅(仮称)です。先ほど天狗山から見ていただいた駅予定地は、この工区の作業ヤードとして使用しています。住宅が近いので、騒音対策にも十分配慮しています」
ここは小樽市郊外の住宅地で、作業ヤードから民家まで25mしかない。坑口やその周辺は、防音パネルでしっかり囲われている。
天神工区の地質は、火山灰を主成分とした火山礫(砂よりも大きい石)を含む火山礫凝灰岩。掘削方法は塩谷工区と同様、発破工法による補助ベンチ付き全断面工法だ。
「住宅近くでの発破工法による作業となりますので、周辺環境への騒音や振動などの影響を測定・調査しており、防音扉も設置して、ご迷惑をおかけしないよう留意しています。また、この工区は坑口から鋼製支保工を建て込んで掘削しています」
切羽では、前方の地質を調査する先進調査ボーリングが行われていた。自然由来の重金属がどれだけ含まれているかを調べるための工程で、約100m先まで調査する。
トンネル外の作業ヤードには、濁水処理施設がある。掘削によって発生した水には泥が混じるため、ここで環境基準を満たす水質に処理して川に流す。処理水を利用した池もあり、鯉が気持ちよさそうに泳いでいた。
「池は、施工を行うJV(建設企業共同体)が準備したもので、処理水の水質を確認する意味もありますし、現場のちょっとした和みにもなっています」





小樽という地域のポテンシャルを伸ばせる交通インフラを目指す
天神工区の本坑入口から振り返ると、新小樽駅(仮称)予定地の向こうに、後志自動車道の高架と毛無山の尾根が見える。
「新幹線は、新駅を発車しますと、朝里トンネルに入ります。あちらの山がくぼんでいる辺りが朝里トンネルの入口です」
朝里トンネルは全長4325mのトンネルで、ほぼ半分の2139mまで掘削が完了した。朝里トンネルは全体の施工を小樽鉄道建設所が担当しているが、本坑へは小さな尾根を越えた作業ヤードから斜坑を通じて入る。このトンネルの特徴は湧水が多いことだ。後志トンネル塩谷工区が毎分2.5t程度のところ、朝里トンネルは最大毎分13tの水が出たこともあった。また、トンネルから地上までの距離を表す土被りは230mほどあるものの、周辺の井戸などをモニタリングして影響を監視しながら掘削を進めている。
切羽の手前では、インバートコンクリートの打設と防水シートの張り込み、および覆工コンクリートの打設が行われていた。インバートコンクリートとは、トンネルの底面に打設される逆アーチ状のコンクリート構造物で、トンネルの安定性を強化し、変形や沈下を防止する。まず底面を掘り下げ、大型台車のような自走式の作業ステージの上からコンクリートを流し込む。
インバートコンクリートを打設すると、続いてトンネル内への漏水を防ぐための防水シートを張り込む。その後内壁に沿った形をしたスライドセントルという装置を導入して、防水シートとスライドセントルの間に覆工コンクリートを打設していく。
最後に、札樽トンネル石倉工区を訪れた。札樽トンネルは全長2万6230m、最大土被り約550mの長大トンネルで、石倉工区はそのうち起点方の約4500mを掘削する。重機を使って土を掘り進む機械掘削によって令和2年11月より掘削を開始し、9月の時点では702mまで掘削が完了。現在は発生土を運ぶためのベルトコンベアの設置準備を行っている。
札樽トンネルの坑口に立つと、新幹線の複線トンネルにしてはやけに坑口が小さい気がした。
決められた線路の上を専用の車両が走る鉄道は、トンネル断面も最小限で済む。その意味でも、鉄道は環境に優れた交通機関だ。
北海道新幹線の開業予定の2030年度末まで10年を切った。
「鉄道は、人の交流を促し地域のポテンシャルを伸ばしていける公共交通機関です。北海道の歴史と文化が詰まった小樽に、1日も早く新幹線をお届けできるよう、安全を心がけて建設にあたります」
旅が好きでコロナ禍以前には全国を旅したという羽生田所長が言った。小樽が、本州から新幹線で気軽に訪ねられる港町に変わる日は、決して遠くない。






